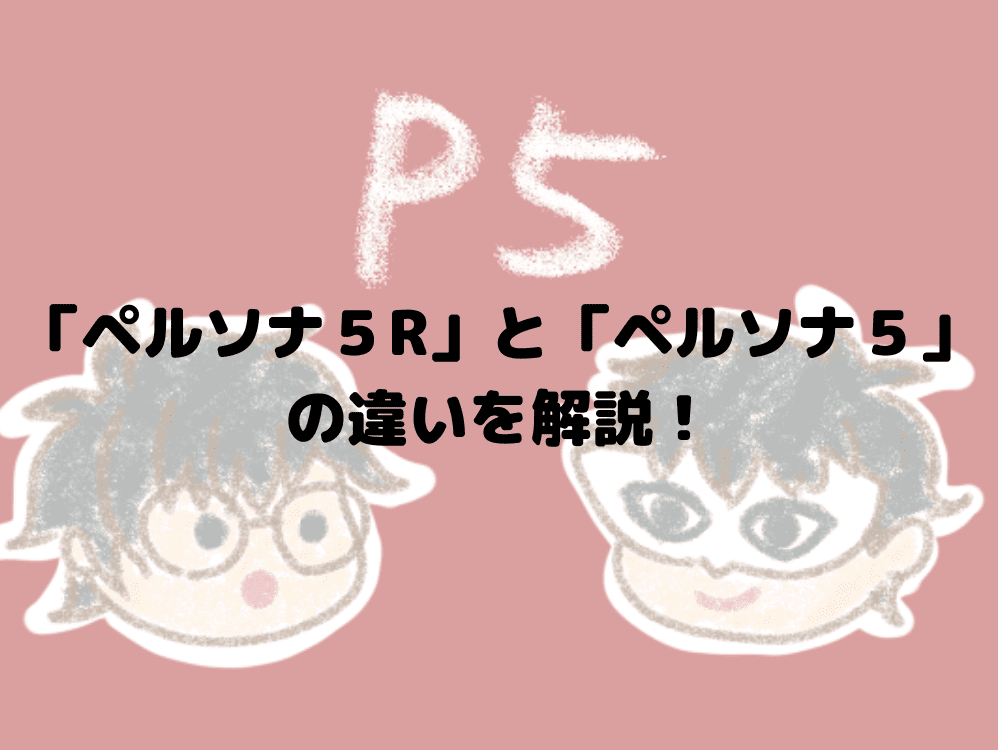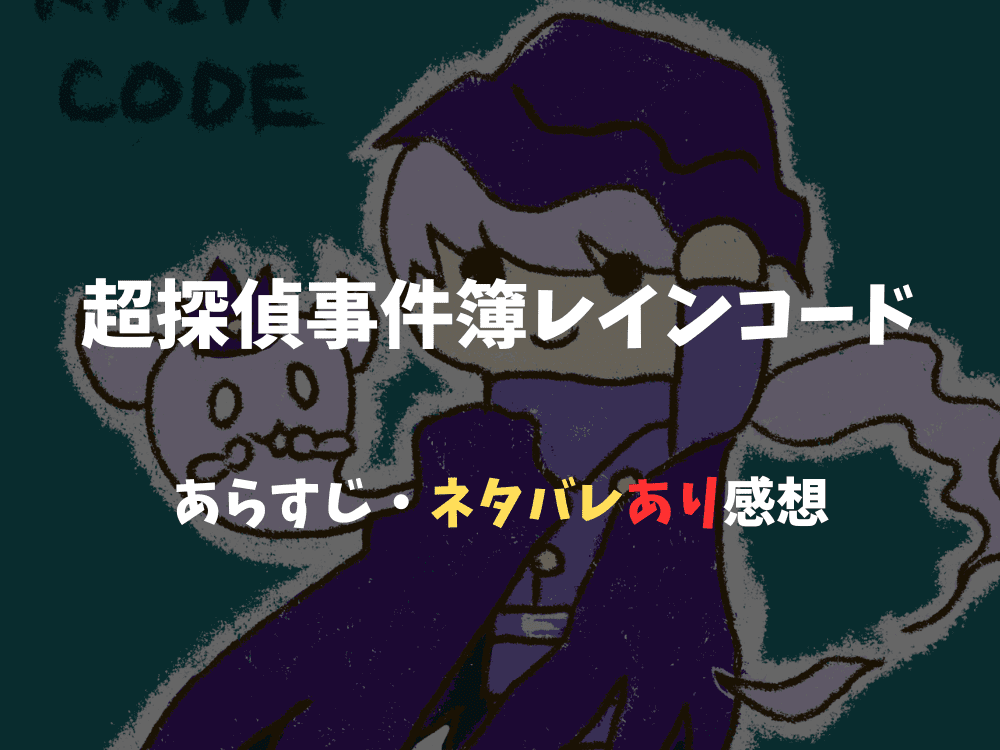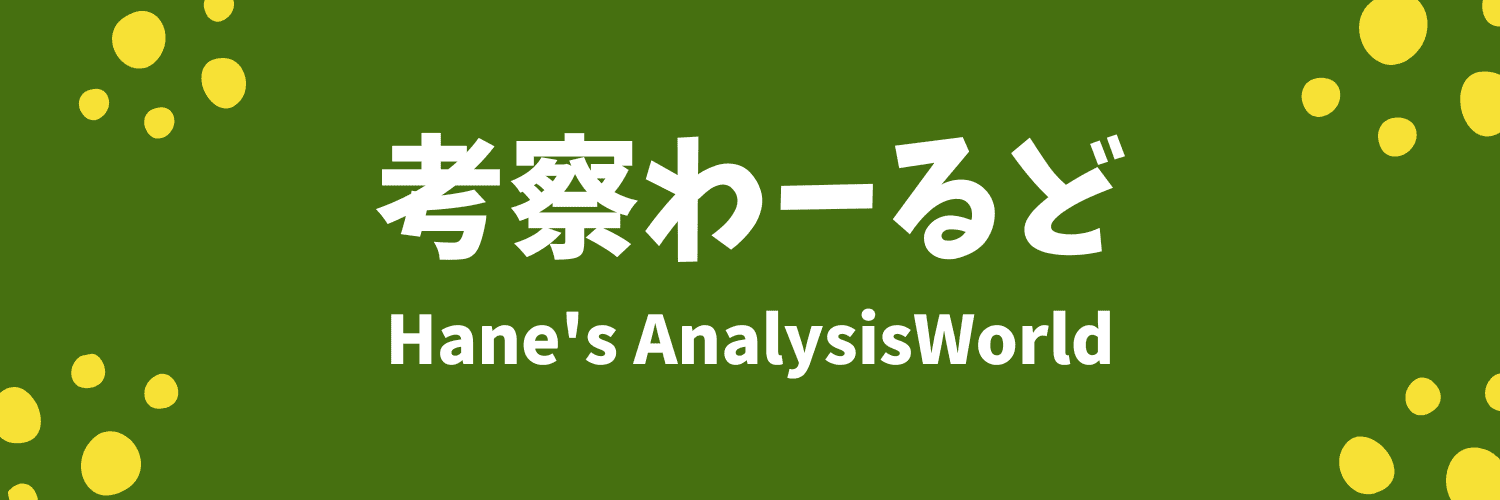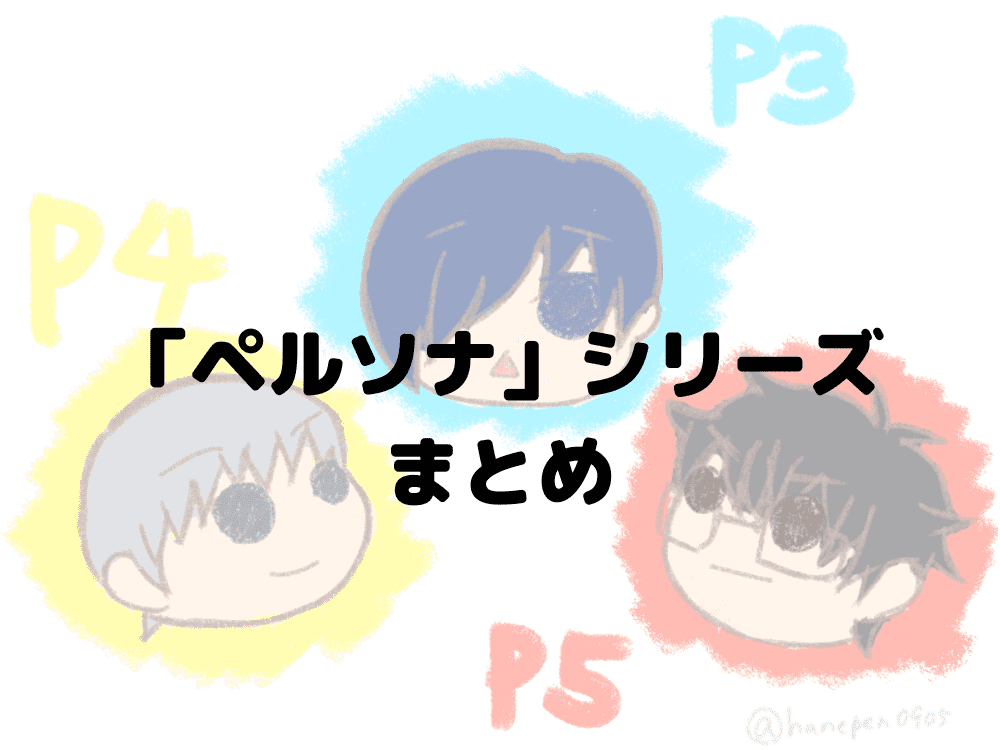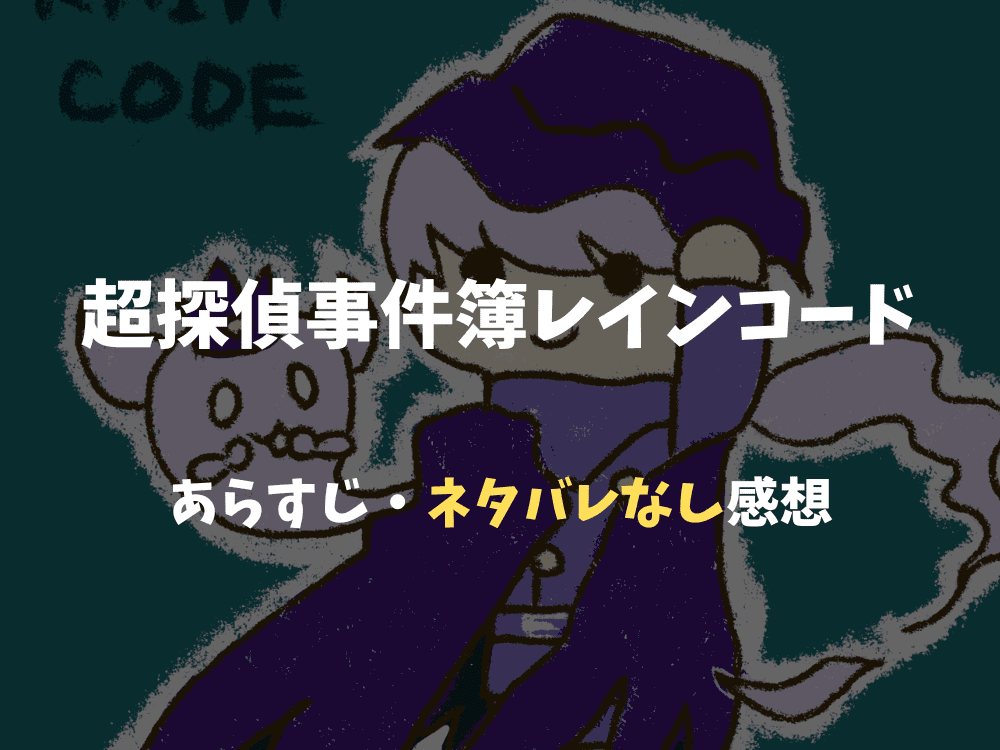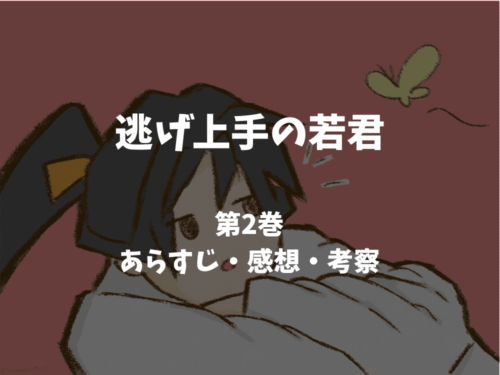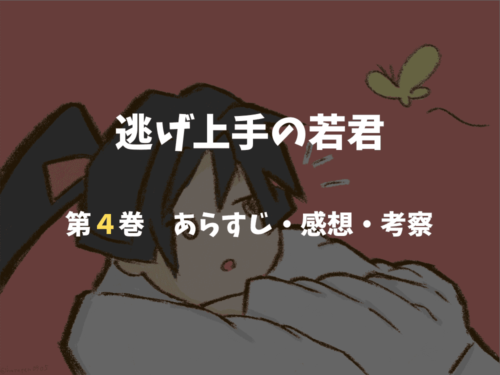中公新書「中先代の乱」感想。乱の前後を分かりやすくまとめてみた
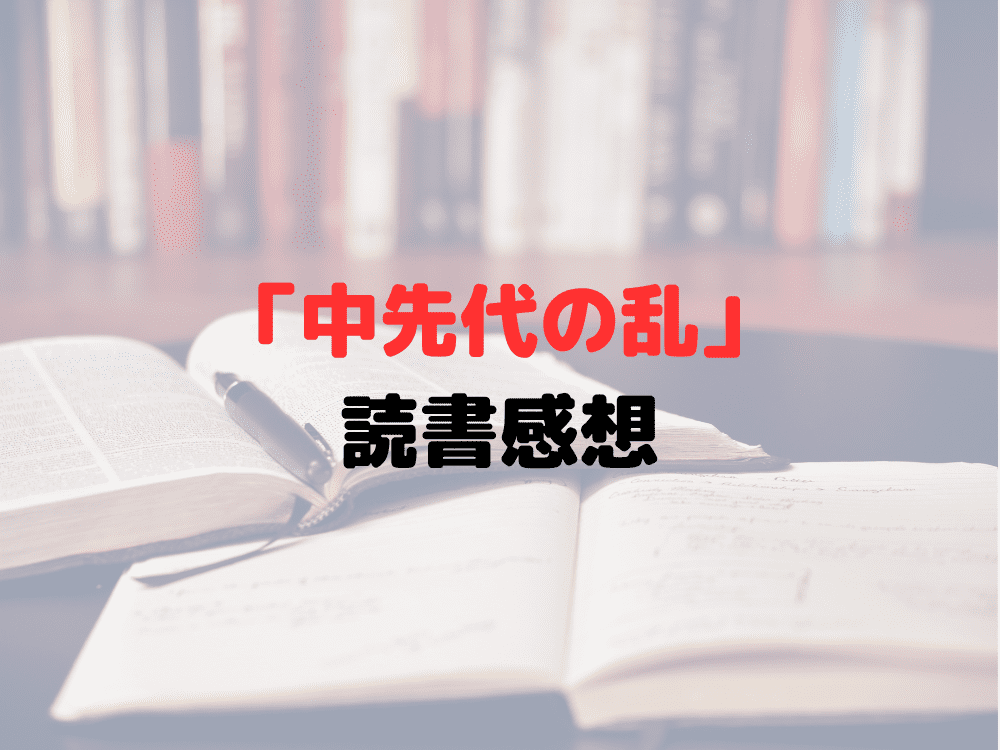
今回は中公新書の「中先代の乱」を読んだ感想と、本書のキーポイントをまとめてみました。
- 「中先代の乱」について、分かりやすいまとめを読みたい
- 北条時行が活躍した鎌倉~南北朝の時代背景を知りたい
- 「中先代の乱」がどんな本なのか知りたい
こんな人向けの記事です。
なお、今回の記事では、中先代の乱を含めた史実の北条時行(ほうじょうときゆき)の生涯について触れています。
また、歴史にあまり詳しくない人間がまとめたものであるので、内容の正確性についてはあまり期待しないでください。
 いぬ
いぬ気になった箇所だけ、ピックアップして紹介しています
詳しい史料や正確性のある答えについては、こちらの著書、および参考文献を参照してください。
中先代の乱とは?
鎌倉幕府滅亡から、足利尊氏が京都に新たな幕府を開く間に起きた戦乱のことです。
鎌倉幕府最高責任者の息子である北条時行が、父と幕府の敵である足利尊氏と激突した「鎌倉時代の天下分け目の戦い」であるとも言えるかもしれません。
中先代の乱については、「魔界探偵脳嚙ネウロ」「暗殺教室」を描いた松井優征さんが漫画化しています。
中先代の乱と北条時行がテーマ!
また、以下の記事でも中先代の乱について簡単にまとめています。
- 北条時行が10歳の時に挙兵。
鎌倉に攻め入って足利尊氏の弟・直義を追い出す
(1回目の鎌倉入り。中先代の乱) - 足利尊氏と直義が合流し、北条時行を鎌倉から追い出す
- 朝廷が足利派・反足利派に分かれて対立したため、時行は反足利派に所属
(南朝の武将になる) - 南朝の武将として斯波家長と戦い、勝利。
(2度目の鎌倉入り) - 近畿地方で南朝の武将として戦い、北朝に敗れる
- 南朝の政策で大船団に加わるも、嵐で船が壊滅。
時行は何とか生き延びる - 信濃で蜂起するも、小笠原貞宗に敗れる
(その後10年ほど行方不明?) - 観応の擾乱(尊氏VS直義)で関東が荒れた際に、時行が関東攻めをする。
(3度目の鎌倉入り) - 足利尊氏の軍に敗れ敗走、鎌倉で足利尊氏に捉えられて処刑される
という流れになっています。
中公新書「中先代の乱」の感想
今回取り上げたこの本は、史料や参考文献が細かく載っており、北条時行についてかなり深く研究されている方が書いたと思われます。
歴史があまり得意でない自分が読んでみた感想としては、年代や登場人物が込み入っており、少し読みにくい構成になっているように感じました。
しかしながら、混乱を極めたであろう当時の様子や、北条時行以外の人物たちについても、かなり詳細に研究されています。
北条時行や、中先代の乱、南北朝時代の背景について詳しく知りたい人は、ぜひ一度読んでみることをおすすめします。
中公新書「中先代の乱」のポイント

- 中先代の乱は、北条時行以外の人物達たちの強い後押しがあった
- 中先代の乱は「寄せ集めの軍」と「台風による大仏倒壊」が敗因?
- 北条時行は史実でも「逃げ上手」である
- 3度目の鎌倉入りの際は、北条時行の後押しをする勢力は弱体化していた
Ad
ポイント①:中先代の乱は必然だった
まずはじめに、中先代の乱が起こったことは、ほぼ必然だったのだろうと読み取れます。
中先代の乱の当時、北条時行は10歳ほどの年齢でした。
にもかかわらず、最終的に足利尊氏の弟である、足利直義を鎌倉から追い出すまで進軍できています。
これは、諏訪頼重など、北条氏を支持して朝廷・足利派の政権を倒そうとする勢力が多かったということでしょう。
地方武士の不満→現政権の倒壊
という流れが、鎌倉幕府滅亡、中先代の乱、南北朝時代の開始に大きく影響を与えていたことになります。
日本史の中では、農業や経済の発展を受けて、権威性から実力重視の時代への節目となるのが北条時行の生きた時代でもあります。
いずれの場合も、教科書には出てこない、力をつけた地方武士が時代の流れを左右していたことになります。
ポイント②:台風による大仏倒壊

北条時行が最終的に負けてしまった原因として、本書では
- 寄せ集めの軍
- 大仏崩壊
が大きいとされています。
北条時行は、朝廷と足利氏に不満を持つ武士たちを集めましたが、寄せ集めの急ごしらえの軍でした。
短期的な利益や不満の解消で戦うことができても、長い間統率の取れた大部隊としてあるにはトップの人物の手腕が欠かせません。
当時10歳の時行はもちろん、異なる地域から急遽合流した軍の連合体では、カリスマ性ある大人でもまとめるのに苦労したであろうことは想像に難くありません。
また、北条時行の鎌倉入りが入った際、朝廷では「打倒北条」の祈祷がされていました。
この際に偶然にも、台風が日本列島に襲来します。
鎌倉の大仏殿で休息をとっていた時行軍の上に、嵐で倒壊した大仏が降ってきたために、大勢の兵士が死傷しました。
当時はまだ、朝廷の神聖性や名家の権威性が強い影響を与えていた時代でもあったため、大仏倒壊は少なくないショックを時行軍に与えたと考察されています。
「天皇が祈祷したために、大仏が倒壊した(=自分たちは罰当たりだ)」
Ad
ポイント③:北条時行は史実でも「逃げ上手」

北条時行は、足利尊氏の一派と何度もぶつかり合います。
しかし、当人は戦場で討ち死にすることなく、何度も窮地を脱出しています。
また、中先代の乱の後、北条時行が南朝に所属した際も危機から逃れています。
天皇の命で各地に南朝方の武士を配属することになった際、北条時行が乗った船が嵐で沈没する事件が起きました。
この時も時行は嵐で亡くなることはなく、無事に生き延びたようです。
ポイント④:3度目の鎌倉入りの際、北条時行軍は大幅な弱体化

北条時行は3度鎌倉入りをすることになります。
その最後の3回目の鎌倉入りの時点では、北条時行を支持する勢力は大幅な弱体化をしていました。
- 諏訪氏の零落
- 南北朝の対立は、最終的に足利尊氏(北朝・室町幕府)が勝利
1度目の鎌倉入りである「中先代の乱」当時は、諏訪頼重などの名門地方武士が北条時行についていました。
しかし、諏訪頼重は中先代の乱の際に死亡し、諏訪氏を引き継いだ諏訪頼継と共に挙兵した際は、小笠原貞宗の軍に敗れています。
(時行は戦乱を逃れ、この語3度目の鎌倉入りを果たします)
さらに、武士が南北朝に分かれて戦っていた時代が終わりに近づきます。
足利尊氏と朝廷の駆け引きや、尊氏と直義の兄弟対立などを経て、足利尊氏は最終的に関東の武士のほとんどを配下に置くことになりました。
信濃~関東での戦で敗れた時行は、鎌倉を脱出して援軍を求めに行く途中で捕まったのではないかと考えられています。
時行が捕まった当時は、北条勢力の多くが捕縛され、弱体化していました。
こうしてみると、鎌倉幕府滅亡から処刑されるまで、北条時行は、逃げながらも生涯足利尊氏と戦い続けたということが分かります。
Ad
まとめ:北条時行は確かに「逃げ上手」だった

- 権威性から実力(軍事・経済力)へシフトしていく時代
- 地方武士をまとめ上げられる力が次代の支配者の条件
- 北条時行の生涯は、時代の変遷の写し鏡
北条時行は北条家得宗という名門中の名門の一族の出身でした。
このため戦乱初期は、幼くても「権威性」でもって地方武士を集めることが容易かったのではないかと考えられています。
しかし、農業や経済の発展に伴い、地方武士が力を持ってくるにつれ、次代の支配者には「地方武士を束ねられる実力をもった者」が求められるようになったのではないでしょうか?
足利尊氏は、京の方針に不満があった関東の武士たちを束ねて、最終的に北条時行を追い詰めています。
北条時行の生涯を追っていくことで、日本史の流れを追っていくことに繋がるのは感慨深いですね。
マンガ「逃げ上手の若君」は、史実とオリジナル要素をミックスさせ、松井優征さんの独自の世界観で人気を博しています。
 いぬ
いぬアニメ化も決定されているよ!
「逃げ上手の若君」について詳しく知りたい人は、この記事もチェックしてね!